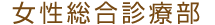-
女性総合診療部を受診される方々へ
病院はハイリスク施設(感染者が多い・感染すると命に関わる人が多くいる施設)です。
医療を継続するために医療者の感染を防ぐ責務もあります。
感染症防止対策についてご協力をお願いいたします。
診察・健診の付き添い(お子さん含む)は感染予防策としてお控えください。特別な事情で付き添いを希望される方は受診時に受付にお申し出ください。
診療の状況や方針は刻々と変化しますので、こまめにホームページをご確認ください。ご来院時のお願い
分娩時の注意事項および分娩立ち合い・病棟での面会について
産科病棟の面会について
※ 産科病棟以外の面会はこちらの「面会時のお願い」をご覧ください。
- 分娩時
-
- 妊婦自身が新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどの伝染性の感染症にかかっている場合、緊急時の対応や様々な処置に時間がかかる可能性があります。このため、妊婦自身が伝染性の感染症と診断された、または類似症状がある場合には検査結果が陰性であっても、分娩方法が変わったり面会制限が厳しくなる可能性があります。
- 分娩時もマスクの着用をお願いいたします。
- 立ち合いはパートナーのみに限らせていただいております。
- 産科病棟の面会時間は以下の通りです。
-
パートナー
- 6時~21時まで面会可能(滞在時間に制限はありません)
- LDRは24時間可能(分娩まで時間がかかることが想定される場合は一度帰宅していただくことがあります)
パートナー以外の家族(上の子含む)
- 全日15:00~17:00/19:00~20:00のみ面会可能
- ただし、入院当日及び産後12時間は面会可能
ご家族以外の方
- 全日15:00~17:00/19:00~20:00のみ面会可能
- 小学生以下の方のご面会はラウンジでの面会も原則として不可です
- 入院中・面会について
-
- 面会中にマスクは外さないでください。特に新生児と接する際にはお気を付けください。
- 面会中の飲食は禁止です。
- 妊婦さんご自身が新型コロナウイルス感染症に感染している、または疑われる場合にはパートナーの分娩立ち合いはできません。また病棟での面会もできません。新生児との接触・面会・母児同室も制限されますが、詳細はその際にご案内します。
-
産科におかかりの方へ「COVID-19の症状と経過について」
-
不妊治療中の方へ(生殖医療センター)
-
2023年11月2日 帝王切開瘢痕症候群外来を開設しました
診療内容
診療内容・特徴
女性総合診療部は、周産期科・一般婦人科・女性外科の3科で構成されています。
当院は、産科医療補償制度に加入し、『児の安全性』と『快適さ』を追求した自然分娩を基調としております。分娩希望の方は、分娩予約が必要です。当院でお引き受けできる妊婦さんは、当院での継続した妊婦健診を受けられる方か、提携しているクリニックで妊婦健診をお受けいただき、34週頃に外来受診していただく里帰り出産の方となります。また、東京都の地域周産期母子医療センターに指定されており、ハイリスク妊婦さんについては病状により適宜お受けしております。詳しくはこちら
一般婦人科・女性外科部門は、がん診療と腹腔鏡手術を得意としています。子宮筋腫などには、子宮鏡下手術のほか放射線科と協力して子宮動脈塞栓術も実施しています。
生殖医療センターは、不妊外来のほか、遺伝子診療部と提携しながら妊娠と薬の相談クリニックも併設しています。センターでは、体外受精、顕微授精のほか、がん治療者の卵や精子の凍結保存ができる体制も整え、子供をつくることに関係するさまざまな問題について、心のサポートも行っています。
対象症例・得意分野・専門分野
- 周産期医療
妊婦健診は、超音波検査を取り入れ、Evidence based medicine(EBM)に基づいた診療を行っています。「母親学級」や多胎の妊婦さん向けの「マルチキッズクラス」などの開催、妊娠時期に応じた助産師外来も併設しており、それぞれの妊婦さんの状況に合わせた快適なマタニティーライフのためのアドバイスを行っています。また多種のパンフレットも作成し、わかりやすい診療を目指しています。カップルで満足のいくお産を目指すために、出産について勉強する「両親学級」を開催し、希望によりパートナーの方の立ち会い出産も行います。分娩室はL.D.Rを取り入れ、陣痛中もお産に集中できる環境を整えております。入院中のお部屋は全室個室となっており、ご家族でゆっくり過ごせるように配慮しております。
入院後は、病棟医が産科チームとして診療を行います。また、NICU(新生児集中治療室)を完備し、産科のみならず、新生児科、麻酔科をはじめとした関連診療科とも連携したチーム医療により、妊娠中の合併症やハイリスク妊娠に対しても安全かつ迅速な対応を目指しています。当院は、東京都の地域周産期母子医療センターとして認定され、母体搬送も受け入れています。詳しくはこちら - 一般婦人科・女性外科
婦人科部門では、腹腔鏡下手術および悪性腫瘍の治療を積極的に実施しています。
また放射線科と協力し、子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術も実施しています。
腹腔鏡は、子宮内膜症や、チョコレート嚢腫や皮様嚢腫など良性と考えられる卵巣腫瘍のほとんどに導入し、腹腔鏡下子宮筋腫核出、腹腔鏡下子宮全摘術も実施しています。2014年には約400件以上の腹腔鏡手術と80件の子宮鏡下手術を行ないました。子宮全摘は年間100例以上が腹腔鏡で行われています。
当院は入院期間が短いのも特徴で、一例をあげると、卵巣の腹腔鏡下手術の入院期間は入院から退院まで 4日間が標準となっています。
2011年11月より、手術支援ロボット 『da Vinci』を導入し、腹腔鏡手術の更なる可能性を追求しています。2012年には年間23件の da Vinci による手術が施行されました。
子宮がん、卵巣がんに関しては、当院は、日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録施設、日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設の認定を受け、また厚労省指定の地域がん診療拠点病院として、悪性腫瘍患者に対する治療に積極的に取り組んでいます。手術待機期間を利用した術前化学療法や、腹腔鏡やda Vinci を用いた低侵襲の手術(主に早期の子宮体癌を対象)も積極的に行っています。
子宮頚部の腫瘍については、必要な方には子宮温存を積極的におこなっています。約120例の円錐切除に加え、適応がありかつ希望される方には広汎性子宮頚部摘出術をおこない妊孕性の温存を図っています。術後引き続き当院の生殖医療センター、妊娠後は周産期センターで管理が継続できるのも当院の特徴と言えます。高い技術や正確な知識に加え、ホスピタリティも大切にして質の高いがん診療を行っていくことを目標にしています。詳しくはこちら
2013年より過多月経の方に対するマイクロウェーブによる子宮内膜凝固術を導入しました。
骨盤臓器脱に関しては、従来法(腟式単純子宮全摘術及び前後腟壁形成術、腟閉鎖など)に加え、腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)も行っております。 - 生殖医療センターについて
生殖医療センターは、2001年5月7日に開設されました。生殖医療センターの中の不妊症診療部門では、2002年度からは顕微受精の実施施設としての申請を日本産科婦人科学会に行い、顕微受精も実施しています。
がんの治療、特に化学療法(抗がん剤治療など)や放射線治療を行うことによる卵巣や精巣への影響、治療後の妊娠の可能性や影響に関して、ご相談をお受けするリプロ外来も開設しています。 - 帝王切開瘢痕症候群外来について
帝王切開瘢痕症候群外来を2023年度より開設しました。
帝王切開瘢痕症候群は帝王切開後に子宮創部に凹みができるとそこに月経血が貯留し、月経困難症や茶色いおりものが長びくといった症状を呈します。2人目不妊の原因として昨今注目されており、当院ではその治療に注力し、腹腔鏡手術および子宮鏡手術を組み合わせて行っています。
なお、帝王切開瘢痕症候群は、国際的にはCesarean scar disorder (CSDi; 帝王切開子宮瘢痕症)として認知されています。当院の手法はnonperfusion hysteroscopyとして、世界有数の国際誌「Fertility and Sterility」に掲載されております。
"Hysteroscopy-guided laparoscopic resection of a cesarean scar defect in 5 steps: the usefulness of nonperfusion hysteroscopy"
妊娠と薬相談クリニックについて
「妊娠と薬相談クリニック」は、妊娠中にご本人が薬を服用したり、パートナーの男性(配偶者)が薬を服用しているときに妊娠した場合など、薬剤の胎児への影響が心配な方のご相談に応じる自費診療の外来です。
受診を希望されるときは、事前に調査票に必要事項を記入し、郵送していただいています。この調査票内容に基づき調査・検索した上でご来院いただき、クリニックでお答えさせていただきます。
なお、ご相談には当院産婦人科医師と薬剤師が同席して相談に応じます。
受診の申し込み方
- 相談を希望される方は、「妊娠と薬相談表」に必要事項をご記入の上、下記の送付先にご郵送ください。
- ご記入いただいた調査票を受け取りましたら、電話またはハガキでご来院日をお知らせいたします。
- 調査票を送付されてから1週間経過しても連絡がない場合には、下記の問い合わせ先のFAX番号まで、連絡がない旨をお知らせください。
- ご来院日は、毎週水曜日午後からになります。
- 「妊娠と薬相談クリニック」が、一層皆様のご期待にそったものになるよう、ご出産後赤ちゃんのご様子をお伺いいたしますので、ぜひご協力をお願いいたします。
調査票送付先・お問い合わせ先
〒104-8560
東京都中央区明石町9-1
聖路加国際病院 トイスラークリニック・妊娠と薬相談クリニック
FAX : 03-5550-2563
電話受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜16:00
遺伝カウンセリングクリニック
詳細は遺伝診療センターのページをご覧ください。
診療実績
外来(生殖医療センターを除く)
| 2022年度 | |
|---|---|
| 初診 | 2,805 |
| 再診 | 43,424 |
| 延べ数 | 46,229 |
婦人科入院
| 2022年度 | |
|---|---|
| 実数 | 914 |
分娩および手術件数
| 2022年度 | 分娩件数 | 1,404 |
|---|---|
| 手術件数 | 1,491 |
| 帝王切開件数 | 499 |
婦人科悪性腫瘍
| 2022年度 | |
|---|---|
| 子宮 | |
| 子宮頸がん(上皮内癌を除く) | 6 |
| 子宮体がん(異型増殖症を除く) | 36 |
| 子宮肉腫 | 2 |
| 卵巣がん(境界悪性含む) | 23 |
| 卵管がん | 0 |
| 原発不明がん | 0 |
| 外陰腫瘍 | 1 |
| 合計 | 68 |
腹腔鏡下手術
| 2022年度 | TLH(筋腫) | 125 |
|---|---|
| TKH(体癌) | 27 |
| 卵巣腫瘍 | 168 |
| 筋腫核出 | 62 |
| ダビンチ | 7 |
| LSC | 1 |
| 異所性妊娠 | 9 |
| その他 | 11 |
| 合計 | 410 |
手術件数
| 2022年度 | |
|---|---|
| 麻酔科管理手術件数 | 1,354 |
| 帝王切開 | 499 |
| 円錐切除術 | 64 |
| 腹腔鏡手術 | 410 |
| 子宮鏡下手術 | 144 |
| 子宮がん | 44 |
| 卵巣がん | 23 |
| ATH(筋腫) | 27 |
| 開腹筋腫核出 | 46 |
| 良性卵巣腫瘍手術(開腹) | 25 |
| 子宮内膜掻把 | 20 |
| 胞状奇胎 | 1 |
| ダビンチ手術 | 23 |
| 産科手術 | 7 |
| 流産手術 | 25 |
| 子宮脱 | 2 |
| その他 | 32 |
外来スケジュール表
※この表はスクロールします
| 医師名/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平田 哲也 | ◯ | ◯ | |||
| 塩田 恭子 | ◯ | ||||
| 齊藤 理恵 | ◯ | ||||
| 秋谷 文 | AM | ||||
| 樫山 智子 | AM | ◯ | |||
| 菅沼 牧知子 | 隔週 | ||||
| 小野 健太郎 | ◯ | ||||
| 岩瀬 純 | AM | ||||
| 松岡 咲子 | AM | ||||
| 横田 祐子 | PM | ||||
| 山本 萌子 | PM | ||||
| 今井 志織 | PM | ||||
| 杉山 美智子 | PM | ||||
| 髙野 理紗 | AM | ||||
| 舘 恵美里 | AM | ||||
| 梶山 くるみ | AM | ||||
| 柳崎 基 | PM | ||||
| 吉井 恵理佳 | PM | ||||
| 渡辺 浩二 | ◯ | ||||
| 佐古 悠輔 | ◯ |
スタッフの詳細情報は名前をクリックしてください。
トピックス
- 日付
- お知らせ
-
2014年9月10日
当院は急性期病院のため、婦人科検診のみの受診はお受けしていません。地域の診療所やクリニックをかかりつけ医とした検診をお勧めしています。かかりつけ医をお探しの方は、当院の医療連携相談室でご相談ください。
-
2011年12月
当科は本年度より、日本産科婦人科学会婦人科腫瘍登録施設、日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設、婦人科悪性腫瘍研究機構(JGOG)登録参加認定施設の認定を受けました。
-
2007年12月7日
新たに不妊治療を希望される患者さんへのお知らせ
2008年1月より、生殖医療センター・不妊外来でも事前予約制とさせていただきます。このため、不妊治療を希望されて新たに受診されても、ただちにはお受けできないことがございます。あらかじめご了承ください。 -
2007年12月7日
2008年1月より、現在通院中の皆さまについても順次事前予約制へと移行させていただきます。このため、前回受診日より3ヶ月以上受診されていない場合は、不妊外来の新しい患者さんとして予約をお取り頂くことになります。予約枠には制限がありますので、受診までに日数がかかります。あらかじめご了承ください。 詳しいことは女性総合診療部へお問い合わせください。 また、凍結胚移植やがん治療者のためのリプロダクション外来受診の方は別途ご相談ください。
生殖医療センターについては、こちらをご参照ください。
メディア掲載情報
論文情報
※この表はスクロールします
| 日付 | 雑誌名 | 論題 | 発表者 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 週刊日本医事新報 5226号(2024年6月8日) | プロからプロへ 帝王切開子宮瘢痕症(CSDi)の診断と手術適応について | 佐古 悠輔 |
| 2024 | 産婦人科の実際 73巻4号(2024年4月1日) | 帝王切開瘢痕症候群に対する腹腔鏡下手術で残存筋層を厚くする工夫 | 佐古 悠輔 |
| 2024 | Cureus | Cervical Stenosis After Hysteroscopic Surgery for Cesarean Scar Disorder | Naofumi Higuchi, Yusuke Sako, Kyoko Shiota, Tetsuya Hirata |
| 2023 | 日本周産期・新生児医学会雑誌 59巻3号 | 妊娠中のリステリア感染の5症例 | 梶山 くるみ、吉田 司、山中 美智子 |
| 2023 | 日本周産期・新生児医学会雑誌 59巻3号 | 完全大血管転位症修復術後妊娠の周産期予後:4症例(5妊娠)の検討 | 梶山 くるみ、山本 萌子、山中 美智子 |
| 2023 | BMC women's health | Process of developing a cervical cancer education program for female university students in a Health and Physical Education teacher training course: an action research. | Yako-Suketomo H, Katayama K, Ogihara A, Asai-Sato M. |
| 2023 | JNCI Cancer Spectr. | Phase I and II randomized clinical trial of an oral therapeutic vaccine targeting human papillomavirus for treatment of cervical intraepithelial neoplasia 2 and 3. | 2. Kawana K, Kobayashi O, Ikeda Y, Yahata H, Iwata T, Satoh T, Akiyama A, Maeda D, Hori-Hirose Y, Uemura Y, Nakayama-Hosoya K, Katoh K, Katoh Y, Nakajima T, Taguchi A, Komatsu A, Asai-Sato M, Tomita N, Kato K, Aoki D, Igimi S, Kawana-Tachikawa A, Schust DJ. |
| 2023 | BMC women's health | Hysteroscopic management of uterine diverticulum after myomectomy: a case report | Yusuke Sako, Tetsuya Hirata |
| 2023 | J Obstet Gynaecol. | Endometritis risk factors after arterial embolisation for postpartum haemorrhage. | Yoshida T, Nagao T, Hayashi K, Yamanaka M. |
| 2022 | The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research | The perinatal outcomes by gestational weight gain range at 30 weeks of gestation among pre-pregnancy underweight women | Takeshi Nagao, Sho Fukui, Sachiko Ohde and Michiko Yamanaka |
| 2022 | 薬局 73巻10号 Page2477-2482(2022.09) |
【不妊とくすりの現在 ここが変わった!治療法・治療薬から保険制度まで】不妊治療のいま 保険適用拡大で何が変わったか(2) 保険適用拡大における不妊の薬物療法 | 平田 哲也 |
| 2022 | Fertility and Sterility 2022 Oct 22;S0015-0282(22)01383-8. doi: 10.1016/j.fertnstert.2022.08.861. | Hysteroscopy-guided laparoscopic resection of a cesarean scar defect in 5 steps: the usefulness of nonperfusion hysteroscopy | Yusuke Sako, Tetsuya Hirata, Mikio Momoeda |
| 2022 | 東京産科婦人科学会会誌 71巻3号 Page620-625(2022.07) |
卵管卵巣膿瘍の診断にて緊急腹腔鏡下手術を施行し虫垂子宮内膜症と診断された1例 | 舘 恵美里、塩田 恭子、杉山 美智子、栗山 恵里沙、川野 さりあ、佐古 悠輔、横田 祐子、岡田 有香、松岡 咲子、百枝 幹雄 |
| 2022 | 東京産科婦人科学会会誌 71巻3号 Page421-424(2022.07) |
巨大・多発子宮筋腫に対する腹腔鏡下・腹腔鏡補助下子宮全摘出術の検討 | 岡田 有香、吉田 司、金城 国俊、杉山 美智子、舘 恵美里、菊地 まほみ、栗山 恵里沙、佐古 悠輔、横田 祐子、松岡 咲子、齋藤 圭介、百枝 幹雄 |
| 2022 | 東京産科婦人科学会会誌 71巻2号 Page227-233(2022.04) |
傍大動脈リンパ節転移で診断された原発不明癌の1例 | 樋口 尚史、齊藤 理恵、菊地 まほみ、百枝 幹雄 |
| 2022 | The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 48巻5号 Page1279-1284(2022.05) |
A case of two ovarian tissue transplantations that led to a biochemical pregnancy in Japan | Sako Yusuke, Akitani Fumi, Shiota Kyoko, Momoeda Mikio |
| 2021 | BMJ Case Report | Benign metastasising leiomyoma with endometrial carcinoma, with a differential diagnosis of metastatic lung cancer | Tsukasa Yoshida, Takeshi Nagao, Risako Ozawa, Kazuhide Hida |
| 2021 | 周産期医学 51巻増刊 Page214-216(2021.12) |
【周産期医学必修知識(第9版)】乳がん合併妊娠(解説) | 塩田 恭子 |
| 2021 | 周産期医学 51巻増刊 Page208-210(2021.12) |
【周産期医学必修知識(第9版)】良性卵巣腫瘍合併妊娠(解説) | 塩田 恭子 |
| 2021 | 周産期医学 51巻増刊 Page146-147(2021.12) |
【周産期医学必修知識(第9版)】インフルエンザ(解説) | 塩田 恭子 |
| 2021 | 東京産科婦人科学会会誌 70巻4号 Page648-652(2021.10) |
癌性腹膜炎の疑いで腹腔鏡下生検を行い、診断に至った結核性腹膜炎の一症例 | 金城 国俊、齋藤 圭介、佐古 悠輔、菊地 まほみ、古明地 康平、高木 駿、吉田 司、小澤 梨紗子、百枝 幹雄 |
| 2021 | 産科と婦人科 88巻10号 Page1259-1263(2021.10) |
婦人科術後に踵に褥瘡を生じた7症例 チームでの予防の取り組み | 美坂 聡樹、杉山 美智子、山本 萌子、白勢 悠記、百枝 幹雄 |
| 2021 | 産科と婦人科 88巻9号 Page1131-1137(2021.09) |
鉄欠乏性貧血およびその治療の現状と課題 医師アンケート調査から | 百枝 幹雄 |
| 2021 | 日本医事新報 5082号 Page48-49(2021.09) |
子宮頸癌の母児間移行 腫瘍の母児間移行の報告はきわめて特殊なので、「私の子どもは大丈夫?」と不安に思っている患者には安心してもらうことが大切(Q&A) | 小野 健太郎、小野 陽子 |
| 2021 | 東京産科婦人科学会会誌 70巻3号 Page561-565(2021.07) |
胎盤部トロホブラスト腫瘍(PSTT)との鑑別に子宮鏡下腫瘍生検が有用であった絨毛癌の1例 | 長尾 健、塩田 恭子、金城 国俊、高木 駿、岡田 有香、横田 祐子、浅見 夕菜、秋谷 文、齋藤 圭介、齊藤 理恵、樋田 一英、百枝 幹雄 |
| 2021 | 東京産科婦人科学会会誌 70巻3号 Page450-454(2021.07) |
リスク低減卵管卵巣摘出術(RRSO)後に卵巣癌を認めた1例 | 美坂 聡樹、塩田 恭子、舘 恵美里、栗山 恵里沙、山本 萌子、長尾 健、岡田 有香、横田 祐子、小澤 梨紗子、秋谷 文、百枝 幹雄 |
| 2021 | 産科と婦人科 88巻7号 Page871-878(2021.07) |
鉄欠乏性貧血およびその治療の現状と課題 患者アンケート調査から(原著論文) | 百枝 幹雄 |
| 2021 | The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research | Effectiveness of 10% povidone-iodine formulation onpreoperative vaginal irrigation | Tsukasa Yoshida, Fumi Akitani, Kuniyoshi Hayashi and Kyoko Shioda |
学会・講演情報
※この表はスクロールします
| 日付 | 学会・講演会名 | 論題 | 発表者 |
|---|---|---|---|
| 2024年718日-20日 | 第66回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 | 顆粒膜細胞腫との鑑別に苦慮した、術後19年の乳癌由来の転移性卵巣腫瘍 | 樋口尚史、髙橋理紗、齊藤理恵、平田哲也 |
| 2024年2月17日-18日 | 第7回日本子宮鏡研究会学術講演会 | 総合病院におけるフルディスポーザブル硬性子宮鏡オペラスコープの導入経験 | 髙野 理紗 |
| 2024年2月17日-18日 | 第7回日本子宮鏡研究会学術講演会 | 子宮鏡下子宮瘢痕部切除術後4か月で発症した遅発性頸管狭窄症 | 樋口尚史 |
| 2024年2月10日-11日 | 第16回ロボット外科学会 | ロボット支援下子宮筋腫核出術術後に生児を獲得した2例 | 樋口尚史、塩田恭子、髙野理紗、杉山美智子、舘恵美里、今井志織、佐古悠輔、横田祐子、松岡咲子、小野健太郎、平田哲也 |
| 2024年2月 | 第21回日本臨床腫瘍学会学術集会 | 地域がん登録統合データを利用した、乳がんサバイバーの長期的健康に関する解析. | 佐藤美紀子, 阪口昌彦, 金村政輝, 森島敏隆, 宮代勲, 片山佳代子 |
| 2024年1月18日 | 技術情報協会Live配信セミナー癒着防止材の各種外科での選定、使用法 | 手術で不妊症をつくらない!産婦人科手術癒着防止材の選択 | 佐古 悠輔 |
| 2023年12月5日 | メルクバイオファーマウェビナー | 初期研修医が思わず産婦人科医になってしまう調節卵巣刺激のまとめ | 佐古 悠輔 |
| 2023年11月26日 | 第146回 関東連合産科婦人科学会総会学術集会 | 妊娠32週に突然発症した痙攣発作を契機に診断された膠芽腫合併妊娠 | 樋口 尚史、金城 国俊、平田 哲也、山中 美智子 |
| 2023年11月26日 | 第146回 関東連合産科婦人科学会総会学術集会 | 骨盤部造影MRI検査が有用であった卵巣境界悪性腫瘍の1例 | 柳崎 基、齊藤 理恵、杉本 圭、宮本 雛子、樋口 尚史、横田 祐子、樫山 智子、秋谷 文、塩田 恭子、平田 哲也 |
| 2023年11月26日 | 第146回 関東連合産科婦人科学会総会学術集会 | 分娩後に1日10Lの多尿を呈し診断された中枢性尿崩症 | 髙橋 理紗、佐藤 亜美、樋口 尚史、髙野 理紗、佐古 悠輔、松岡 咲子、平田 哲也、山中 美智子 |
| 2023年9月14日-16日 | 第63回 日本婦人科内視鏡学会 | 術前に子宮鏡検査を施行した子宮体癌症例の再発率に関する検討 | 髙木 駿 |
| 2023年9月14日-16日 | 第63回 日本婦人科内視鏡学会 | 腹腔鏡下子宮全摘術とロボット支援下子宮全摘術の患者QOL | 樋口尚史 、吉田司 、隅野幹斉 、柳崎基 、髙野理紗 、杉山美智子 、舘恵美里 、今井志織 、佐古悠輔 、横田祐子 、松岡咲子 、小野健太郎 、齊藤理恵 、塩田恭子 、平田哲也 |
| 2023年9月14日-16日 | 第63回 日本婦人科内視鏡学会 | ロボット支援下子宮筋腫核出術術後に生児を得た2例 | 樋口尚史、塩田恭子、柳崎基、髙野理紗、杉山美智子、舘恵美里、今井志織、佐古悠輔、横田祐子、松岡咲子、小野健太郎、平田哲也 |
| 2023年9月14日-16日 | 第63回 日本婦人科内視鏡学会 | 全腹腔鏡下子宮全摘術 4年後に腟断端内膜症を発症した一例 | 髙野理紗、松岡咲子、樋口尚史、杉山美智子、舘恵美里、今井志織、佐古悠輔、横田祐子、樫山智子、秋谷文、小野健太郎、塩田恭子、齊藤理恵、平田哲也 |
| 2023年9月14日-16日 | 第63回 日本婦人科内視鏡学会 | 診断に苦慮し術中妊娠検査薬の使用が診断補助となった卵巣妊娠の一例 | 杉山美智子、樋口尚史、髙野理紗、舘恵美里、今井志織、佐古悠輔、横田祐子、松岡咲子、秋谷文、平田哲也 |
| 2023年9月14日-16日 | 第63回 日本婦人科内視鏡学会 | 帝王切開子宮瘢痕症(CSDi)の新基準と子宮鏡・腹腔鏡手技 これから始めよう! ~当院の取り組みと工夫~ | 平田哲也 |
| 2023年9月14日-16日 | 第63回 日本婦人科内視鏡学会 | 腹腔鏡×子宮鏡 二刀流時代はすぐそこに 道半ばの青年が作成したW認定医獲得への最短経路図 | 佐古悠輔 |
| 2023年9月14日-16日 | 第63回 日本婦人科内視鏡学会 | 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術におけるnonperfusion hysteroscopyの有用性と創傷治癒に配慮した減張縫合 | 佐古悠輔 |
| 2023年8月 | 第47回日本女性栄養・代謝学会学術集会 | シンポジウム 多角的視点から考える婦人科癌患者の栄養代謝 「がんサバイバーの栄養と治療者の役割」 | 佐藤 美紀子、高橋俊文、鈴木直 |
| 2023年7月 | 第65回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 | 乳がんサバイバーの子宮体がん罹患に関する疫学調査〜地域がん登録データを利用した大規模コホート調査〜 | 佐藤美紀子, 阪口昌彦, 片山佳代子, 西村 允邦, 川名敬 |
| 2023年7月27日-28日 | 第41回 日本受精着床学会総会・学術講演会 | レトロゾール併用アンタゴニスト法におけるtrigger法による卵子成熟率の違いについて | 秋谷文、高橋佳奈、村上優賀里、今村明日香、飯島圭子、池田文子、粟田絵里加、中村希、杉山美智子、佐古悠輔、横田祐子、大垣洋子、堀内洋子、塩田恭子、平田哲也 |
| 2023年7月27日-28日 | 第41回 日本受精着床学会総会・学術講演会 | 帝王切開瘢痕症候群に対する腹腔鏡下手術で残存筋層を厚くする工夫 | 佐古悠輔、平田哲也 |
| 2023年7月7日-9日 | 第47回 日本遺伝カウンセリング学会学術集会 | PGT-AでB判定の胚を移植した3例 | 佐藤亜美、佐古悠輔、横田祐子、岡田有香、鈴木美慧、青木美紀子、堀内洋子、熊耳敦子、小笠原智香、山中美智子 |
| 2023年7月7日-9日 | 第47回 日本遺伝カウンセリング学会学術集会 | 子宮体癌により死亡に至ったLi-Fraumeni症候群の1例 | 秋谷文、佐古悠輔、岡田有香、横田祐子、佐藤亜美、喜多久美子、竹井淳子、堀内洋子、酒見智子、小笠原智香、熊耳敦子、鈴木美慧、大川恵、青木美紀子、塩田恭子、山中美智子 |
| 2023年6月 | 日本がん登録協議会第32回学術集会 | 地域がん登録データを用いた本邦の重複がん疫学調査と結果活用への課題. | 佐藤美紀子, 阪口昌彦, 金村政輝, 森島敏隆, 西村允邦, 宮代勲, 川名敬, 片山佳代子 |
| 2023年6月10日 | 第157回 関東生殖医学学会 | 帝王切開瘢痕症候群に対する腹腔鏡下手術での二層縫合 | 佐古悠輔、平田哲也 |
| 2023年5月20日-21日 | 第39回産婦人科感染症科学会 | サルモネラによる卵巣膿瘍に対して腹腔鏡下ドレナージ術を施行した1例 | 樋口 尚史 |
| 2023年5月12日‐14日 | 第75回 日本産科婦人科学会学術講演会 | 妊娠中のリステリア感染症と周産期予後:5例での検討 | 梶山くるみ、吉田司、佐藤亜美、斎藤理恵、塩田恭子、山中美智子、平田哲也 |
| 2023年5月12日‐14日 | 第75回 日本産科婦人科学会学術講演会 | 妊娠中に肺血栓塞栓症を発症し開胸血栓除去術を施行した2例 | 佐藤亜美、山岡恵美里、山本萌子、松岡咲子、菅沼牧知子、塩田恭子、山中美智子、平田哲也 |
| 2023年5月12日‐14日 | 第75回 日本産科婦人科学会学術講演会 | 卵子提供後妊娠47例の周産期予後の検討 | 隅野 幹斉、佐藤亜美、舘恵美里、山本萌子、松岡咲子、菅沼牧知子、塩田恭子、齋藤理恵、山中美智子、平田哲也 |
| 2023年4月19日 | 第11回 HOPEカンファレンス | 理想的な卵巣組織移植手技への模索~最適な移植位置とは~ | 佐古 悠輔 |
| 2023年2月25日 | 第13回 日本がん・生殖医療学会 | レトロゾール併用アンタゴニスト法における採卵決定時エストラジオール値の検討 | 吉田 司、佐古 悠輔、横田 祐子、岩瀬 純、堀内 洋子、秋谷 文、塩田 恭子、平田 哲也 |
| 2023年2月25日 | 第404回 東京産科婦人科学会 | タモキシフェン内服中の子宮内膜ポリープの転帰に関する検討 | 高野 理紗、吉田 司、杉山 美智子、舘 恵美里、佐古 悠輔、横田 祐子、松岡 咲子、井上 知子、秋谷 文、齊藤 理恵、塩田 恭子、平田 哲也 |
| 2023年1月21日-22日 | 第44回 日本エンドメトリオーシス学会学術講演会 | 子宮内膜症、子宮腺筋症合併妊娠における周産期合併症と周産期リスク | 平田 哲也 |
| 2023年1月18日-22日 | 第9回 日本子宮鏡研究会学術講演会 (カールストルツ賞受賞) |
子宮筋腫核出術後に帝王切開瘢痕症候群類似の症状を呈した一例 | 佐古 悠輔、平田 哲也 |
| 2023年1月18日-19日 | 第6回 日本子宮鏡研究会学術講演会 | 術前に子宮鏡を施行した子宮体癌症例の再発率に関する検討 | 髙木 駿、吉田 司、金城 国俊、古明地 康平、杉山 美智子、舘 恵美里、今井 志織、佐古 悠輔、横田 祐子、松岡 咲子、井上 知子、塩田 恭子、平田 哲也 |
| 2022年11月3日-4日 | 第67回 日本生殖医学会学術講演会総会 | 腹腔鏡下卵巣組織移植後に2度の生化学的妊娠からTh1/Th2比の異常高値が判明した一例 | 佐古 悠輔、秋谷 文、横田 祐子、塩田 恭子 |
| 2022年11月3日-4日 | 第67回 日本生殖医学会学術講演会総会 | エストロゲン感受性乳癌患者に対するアロマターゼ阻害薬併用卵巣刺激の影響~Propensity scoreによる背景マッチングを用いた比較検討~ | 吉田 司、佐古 悠輔、横田 祐子、堀内 洋子、秋谷 文、塩田 恭子、平田 哲也 |
| 2022年10月28日 | 全国プロゲスチンWeb講演会II | 月経困難症、子宮内膜症の治療におけるジエノゲストの位置づけ | 平田 哲也 |
| 2022年10月22日 | 第140回 播州産婦人科セミナー | 子宮内膜症、子宮腺筋症合併妊娠でわかってきたこと | 平田 哲也 |
| 2022年9月8日-9月10日 | 第62回 日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 | 当院における卵管捻転8例の臨床的特徴の検討 | 舘 恵美里、佐古 悠輔、吉田 司、金城 国俊、古明地 康平、髙木 駿、杉山 美智子、齋藤 圭介、塩田 恭子、平田 哲也 |
| 2022年9月8日-9月10日 | 第62回 日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 | 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術における子宮鏡併用 5step病変切除法 <非潅流子宮鏡の有用性> | 佐古 悠輔、平田 哲也、百枝 幹雄 |
| 2022年9月8日-10日 | 第62回 日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における、修練年数を考慮した手術適応に関する検討 | 吉田 司、塩田 恭子、林 邦好、平田 哲也 |
| 2022年8月5日-7日 | 第74回 日本産科婦人科学会学術講演会 | COVID-19罹患妊娠に対する抗凝固療法中に腹直筋下縁巨大筋膜下血腫を生じ緊急手術を要した妊婦の1例 | 舘 恵美里、杉山 美智子、栗山 恵里沙、川野 さりあ、浅見 夕菜、岡田 有香、松岡 咲子、小山田 瑞紀、菅沼 牧知子、齊藤 理恵、山中 美智子、百枝 幹雄 |
| 2022年8月5日-7日 | 第74回 日本産科婦人科学会学術講演会 | 子宮手術既往妊娠における子宮筋層評価の重要性 子宮筋腫核出後妊娠の穿通胎盤により自宅で出血死した症例 | 山中 美智子、百枝 幹雄 |
| 2022年8月5日-7日 | 第74回 日本産科婦人科学会学術講演会 | 当院で卵巣組織凍結を選択した乳癌症例の検討 | 佐古 悠輔、塩田 恭子、秋谷 文、横田 祐子、佐藤 亜美、岡田 有香、堀内 洋子、山中 美智子、百枝 幹雄 |
| 2022年8月5日-7日 | 第74回 日本産科婦人科学会学術講演会 | 妊娠初期の高血糖から先端巨大症の診断に至った一例~血糖異常高値から二次性糖尿病を疑う~ | 吉田 司、兵藤 博信、水野 吉章、賀 博美、江 沙音、新田 慧、熊澤 理紗、岩佐 加波、彦坂 慈子、船倉 翠、今田 信哉、久具 宏司 |
| 2022年6月18日-19日 | 第143回 関東連合産婦人科学会総会・学術集会 | 経腟採卵における術中疼痛評価の新指標 Body Movement Scale~痛みのない採卵を目指して~ | 吉田 司、佐古 悠輔、横田 祐子、岡田 有香、岩田 純、堀内 洋子、秋谷 文、塩田 恭子、百枝 幹雄、平田 哲也 |
| 2022年6月11日 | 第4回 日本不育症学会学術集会 | 抗リン脂質抗体症候群合併妊娠に対するヘパリン代替薬選択の検討~Systematic Review of Literature~ | 吉田 司、齋藤 圭介、鈴木 容子、河合 富士美、齊藤 理恵、塩田 恭子、山中 美智子、平田 哲也 |
| 2022年5月7日-8日 | 第38回 日本産婦人科感染症学会 | 婦人科術前腟洗浄における、ポピドンヨード至適濃度の検討~日本の市販濃度は消毒液として適しているのか~ | 吉田 司、秋谷 文、林 邦好、齋藤 圭介、齊藤 理恵、樋田 一英、山中 美智子、百枝 幹雄、塩田 恭子 |
| 2021年12月2日-4日 | 第34回 日本内視鏡外科学会総会 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術でMyoma psudocapsuleを温存し出血量を軽減させるための工夫 | 佐古 悠輔 |
| 2021年9月11日-13日 | 第61回 日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術に向けた運針トレーニングとポイント | 佐古 悠輔、斎藤 圭介、岡田 有香、横田 祐子、松岡 咲子、舘 恵美里、杉山 美智子、百枝 幹雄 |
| 2021年4月22日-25日 | 第73回 日本産科婦人科学会 | Effectiveness of Povidone-Iodine formulation on preoperative vaginal irrigation ~On comparison of 10% and 1% povidone-iodine~" | Tsukasa Yoshida, Fumi Akitani, Kuniyoshi Hayashi, Keisuke Saito, Rie Saito, Kazuhide Hida, Michiko Yamanaka, Mikio Momoeda, Kyoko Shioda. |
| 2020年11月14日-15日 | 第140回 関東連合産婦人科学会総会・学術集会 | 分娩後異常出血に対する動脈塞栓術施行後の子宮内膜炎発症に関与する因子の検討 | 吉田 司、長尾 健、秋谷 文、齋藤 圭介、齊藤 理恵、樋田 一英、塩田 恭子、山中 美智子、百枝 幹雄 |
| 2020年8月27日-29日 | 第60回 日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 | 術中回収式自己血輸血を用いたLMの拡大適応 | 吉田 司、小野 健太郎、秋谷 文、斎藤 圭介、斎藤 理恵、樋田 一英、塩田 恭子、山中 美智子、百枝 幹雄 |
関連著書
患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん治療ガイドライン第3版
日本婦人科腫瘍学会編、Q 61.婦人科がんを治療した後、性生活はどう変わるでしょうか?
佐藤 美紀子、金原出版、発行日:2023/7/15