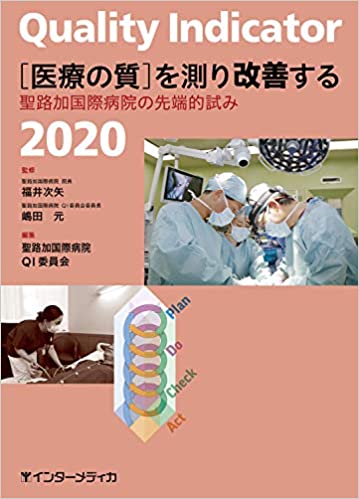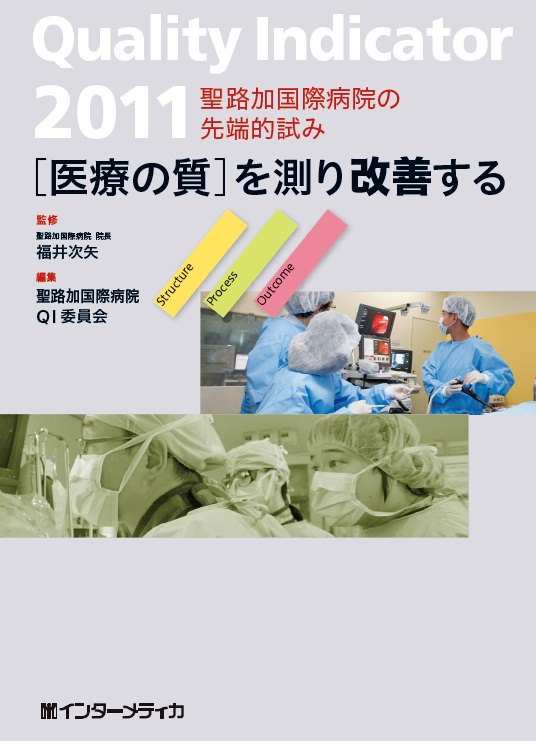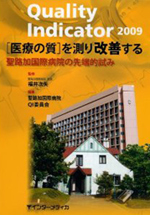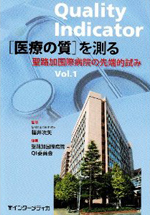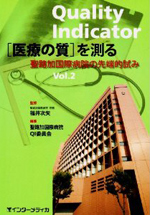Quality Indicator(医療の質)
聖路加国際病院では、医療の質指標(Quality Indicator:QI)を用いた医療の質改善活動[QI(Quality Improvement)活動]を一冊の本にまとめて出版してきました。
2024年からは多くの方がいつでもアクセスできるようにホームページに公開することといたしました。
2022年度までのQI指標の詳細・測定結果は書籍として出版しています。
St.Luke's Quality and Healthcare Report 2006
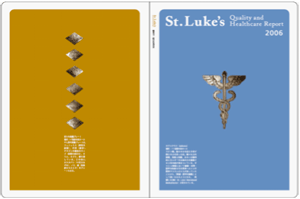
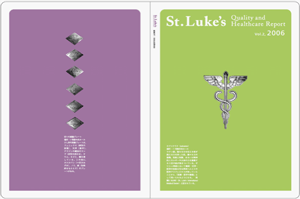
ESQR(欧州質研究学会)よりベストプラクティス賞を受賞
当院が取り組んでまいりました「医療の質を表す指標の測定・公開と改善活動」が高く評価され、この度、2016年欧州ベストプラクティス賞を受賞しました。同賞は、Quality CultureならびにQuality Improvementを促進することを目的としたESQR(欧州質研究学会)が主催し、世界中の企業、組織の中で様々な分野における顕著な質改善運動の功績が認められた団体を表彰するものです。授賞式は、6月4日(土)にベルギーの首都ブルッセルにて開催され、75の企業、組織とともに当院が表彰されました。
プレスリリース
国際病院連盟賞最高位賞を受賞
当院が取り組んでまいりました「医療の質を表す指標の測定・公開と改善活動」が高く評価され、この度、国際病院連盟賞最高位賞を受賞しました。同賞は、国際病院連盟が主催し、世界中の病院の活動、取り組みで、顕著な功績が認められた病院を表彰するもので、今年が第1回目となります。授賞式は、2015年10月6日に米国シカゴで開催されました国際病院連盟主催の世界病院会議において執り行われました。
プレスリリース